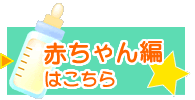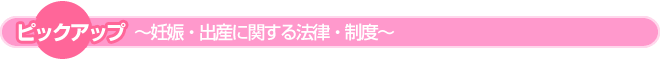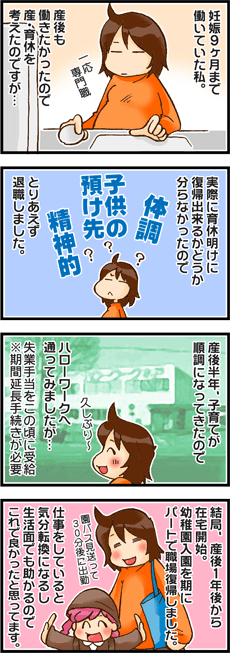printSubMenu();
?>
printLectureMtnPickupMenu();
?>
| 妊娠を機に仕事を辞めてしまう女性は多いですが、妊娠中はもちろん出産後も働き続けたい場合、 法制度を知っておいた方がいいでしょう。 労働基準法、男女雇用機会均等法で、働く妊婦を守る制度や法律が定められています。 大きな会社ならともかく、小さな会社で前例がないと産・育休やその他の待遇を受けづらいという部分はあるでしょうが、 働き続けたい意志があるのなら会社に交渉するためにも必要な知識を身につけておきましょう。 |
妊婦が会社に請求できる制度
| つわりやその他の症状で体調がすぐれないとき、ぜひ活用しましょう。会社で応じない場合は労働基準監督署に相談を。 ・通勤ラッシュを避けて時差通勤できる ・労働時間を短縮できる、休日・時間外・深夜労働の免除 ・職場の配置転換、作業の負担が軽い部署への異動 ・休憩時間を増やす ・健診を受けるための時間を確保できる(妊娠週数の健診回数によって月1~4回) |
三都さんの場合・・・ |
|

|
|
|
|
|
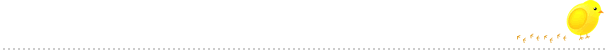
産休(産前産後休業)
会社に勤務する妊娠中の女性は、産前(出産予定日前)6週(多胎妊娠の場合14週)から産後8週まで休みをとれます。産後8週の間、会社側は産婦を就業させることができないことになっていますが、産後の経過が順調と医師が判断し産婦にも働きたい意志がある場合は、産後6週から働くことができます。

出産手当金
勤務先の健康保険か共済組合に1年以上加入し、産前産後休暇をとって仕事を続ける場合、出産手当金がもらえます。最大で出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)と出産日後56日の合計98日間、給与日額(給与を30で割った額)の2/3が支給されます。必要な書類は会社から受け取ることができるので、早めに手配しておきましょう。出産時に医師や助産師に記入してもらう欄もあるので、入院時に病院や産院に持参するのを忘れずに。

育休(育児休暇)
育休は、産後休暇の翌日から赤ちゃんが1歳になる日までとることができます(産後57日目から誕生日の前々日まで)。会社によっては3歳までとれるところ、保育園に入れない場合に延長を認めてくれるところもあります。育休は女性だけでなく男性も取得可能。雇用保険に加入し、育休に入る前の2年間のうち、ひと月に11日以上働いた月が12ヵ月以上あれば育休中に育児休業給付金が支給されます。